こんにちは、司法書士試験合格者のつばさです。
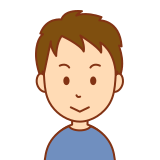
司法書士試験の挑戦を検討している。難しいと聞くけどどうしよう
私は行政書士試験後に司法書士試験に挑戦しました。
結果、合格することが出来、良い選択をしたと思っていますが、大変な面もありました。
それは司法書士試験が難しく、厳しい面も多いためです。
司法書士試験の受験をオススメする情報は予備校等含め多くありますが、厳しい一面、大変な一面を書いた記事は少ないように感じました。
ネガティブな情報も含めて受験するかどうかを検討したい方に向け、厳しい一面に焦点をあて記事を書きたいと思います。
※司法書士になりたい!という明確な目標がある方は迷わず司法書士試験に挑戦しましょう。
前置き
司法書士試験は合格率5%の難関試験です。合格率だけ見れば「自分に出来るのか…」と不安になってしてしまいますが、正しい方向で努力すれば十分合格を目指せる試験です。
私自身、働きながら、子育てしながらと比較的時間がない中でしたが3回目の受験で合格することが出来ました。
私自身、司法書士試験に合格して可能性が広がったので、多くの方に司法書士試験に挑戦して欲しいと思っています。
私は伊藤塾
![]() を利用して合格しました。時間が限られる社会人受験生だったので予備校の活用はマストでした。
を利用して合格しました。時間が限られる社会人受験生だったので予備校の活用はマストでした。
伊藤塾はテキストが本当によくまとまっていて分かりやすいというのが一番の特徴です。私は合格した年の直前期はテキストの読み込みばかりしていました。
(サンプル 公式サイト・伊藤塾オリジナルテキスト
![]() )
)
効率良く学ぶためにも予備校の活用をオススメします。
司法書士試験の厳しい一面について
私自身がそうであったように、行政書士試験や宅建士試験からのステップアップで司法書士試験を検討している方も多いと思います。
いくら難しい試験とはいえ、挑戦しない限り「合格」はありません。挑戦しようという気持ちがあるのであればぜひ、挑戦をオススメします。
ただし、挑戦するのであれば慎重に検討をすることをオススメします。
なぜなら司法書士試験は合格まで3〜5年程度掛かることが多く、受験回数が増えると「あと何回受ければいいんだ、と出口の見えないトンネルを彷徨うことになり、
司法書士試験から撤退してするにしても、その時点で既にかなりの多くの時間やお金を掛けたものが回収出来なくなり、勉強を辞めるに辞めれないという、「進むも地獄、退くも地獄」という閉塞状態に陥ってしまう可能性があります。
私は3回目で受かりましたが2回目は1点差で落ちています。今回受かったからいいものの、落ちていたら正直撤退も考えたかもしれません。
合格まで掛かる年数について
これは可処分時間や他の資格試験の経験の有無、本人の努力によるため一概に言うのは難しいですが
合格までは一般的に3〜5年程度掛かることが多く、周りの合格者に実際に聞いてもそれくらいの期間が掛かった方が多い印象です。
10年でやっと合格したという人もいます。
※勿論、1年以内で合格する方もいます。割合としては少ないかもしれませんが。
私は3回目の受験(勉強期間は約2年半)で合格することが出来ましたが、私の場合はそれ以前に行政書士試験の経験があり、その下地がありました。
民法、憲法、会社法は一応勉強経験がありましたし、既に勉強習慣は定着していました。
そのため、行政書士試験の経験が無い状態で3回目で受かったかは正直微妙です。
そのため合格3〜5年くらい(もしくはそれ以上)試験勉強をするかもしれないという厳しい面があります。
他の合格者の方が言っていて、
私も同感ですが司法書士試験の受験時代は修行僧のような生活になります。
色々なものを我慢してその時間を勉強に費やすためです。
その生活が3〜5年、もしくはそれ以上続くかもしれないという覚悟が必要です。
合格率
司法書士試験の合格率はおよそ5%です。
逆に言うと95%の人が落ちる試験です。
令和5年の試験でいうと、受験者13,372人に対して12,677人は落ちる試験です。
足切り点がある
司法書士試験には①択一式試験(午前)、②択一式試験(午後)、③記述式試験それぞれに足切り点があります。
おおよその目安として、択一式は7割程度、記述は5割程度が基準点になりますがいくら他の点数が良くても足切りに引っ掛かるとその時点で不合格になります。
私の例でいうと、2回目の受験時、択一午前で35問中31問正解、択一午後で35問中34問正解し、総合点では合格点を13点も上回ったのに記述式で1点基準点に足りず落ちた経験があります。
いくら合格点を上回っても、各科目をバランスよく得点しないと足切りになり不合格になるという厳しい面があります。
周りの競争相手
既に述べた通り司法書士試験は難しい試験であるため周りの競争相手も「相当な覚悟」で臨んできます。
合格者の方とお話していて、「試験のために仕事を辞めました」という方、全くの専業では無いまでも「フルタイムでの勤務を辞めパートや契約社員で、勉強時間を確保した」方もいました。
また、毎日10時間、勉強してましたという方もいました。
生半可な勉強では合格するのは難しいことがわかります。
それくらいの決意と覚悟を持って受験する相手と戦っていく必要があります。
試験は相対評価
司法書士試験は相対評価の試験です。周りの受験生と競争して、上位5%に入らないと受かりません。
いくら自分の点が良くても他の人も点がいいと落ちてしまいます。
※例えば行政書士試験は絶対評価なので180点取れば合格出来ます。
そして競争する相手は先程書いたような「並々ならぬ覚悟で試験に臨んでいる人達」です。
そのような方々と競争して競り勝つ必要があります。
そのため、勉強してたらいつか受かるような試験でなく、努力の方向を誤ると、何年経っても努力が報われない可能性もあり受験が長期化する要因にもなります。
受験者数
10年単位で見ると減少していますがここ4年で見ると受験者数は増加傾向です。
ただし、その分合格者も増えており、合格率は横ばいであるため、受かりにくくなっているとは言えない状況です。
ただし、資格試験は不況により人気が出るという傾向もあります。
不確実性も高い現代において今後、合格者数より受験者の増加率が高まると合格率が下がってくるという可能性は否定出来ません。
あくまで憶測の話です。
色々なものが犠牲になる
予備校等でよく言われる司法書士試験に必要な勉強時間は3000時間です。
当然ですが3000時間勉強したからといって受かる訳ではありません。
それに司法書士試験は年一回の試験であるため合格が1年遅れるごとに勉強時間はどんどん増えていきます。
裏返すと単純に勉強時間は他のことに時間が使えなくなります。
本来は家族や友人との時間、自分の趣味の時間、仕事などに充てられていたはずの時間が勉強時間で消えていきます。
私の例で言いますと
・家族との時間が減った
・自分の趣味の時間は一切無くなった
・飲み会は全く行かくなった
・友達と会う回数が劇的に減った
・ゆっくり何も考えず休むことが出来なくなった
等の弊害があります。
私は働きながら、子育てしながらで時間が取れない中での受験だったので、とても息苦しい生活になってしまいました
「専業受験生で勉強に全てを費やせるんだ、だから損はしないんだ」という方でも、その勉強時間をバイトや仕事にあてていたら?例えば時給1000円のアルバイトでも3000時間を掛けると300万になります。
それだけの時間を損失する可能性があります。
勿論、司法書士試験に合格し、司法書士としてキャリアを積めば十分お釣りがくる出費だとは思いますが。
お金が掛かる
予備校代、書籍の購入などでお金が掛かります。
私の場合、おおよそ50〜60万でした。
私が司法書士試験に掛かった費用については以下記事でまとめています。
LEC、伊藤塾などの大手の入門講座ではそれだけで30〜50万程度掛かることが多く予備校を利用するならある程度のお金が必要です。
予備校を利用したいがなるべく費用を掛けたくない方はスタディングがオススメです。
独学でやれば安くは出来ますが、司法書士試験は合格率5パーセントの難関試験であり、効率的に学習を進めることが出来なければ合格まで10年選手となる可能性も大いにありえます。
目に見える出費は少なくても、合格まで5年以上掛かると時間的コストが大きすぎます。
上記理由から、司法書士試験は宅建や行政書士試験に比べて予備校利用の方がほとんどです。(私がお会いした合格者では独学は1割以下)
周りが司法書士試験に精通した有名、ベテラン講師から体系的に、最短距離で教わった方ばかりの中、その人達と競争して、独学で上位5パーセントに入れる自信のある方は独学でも良いと思います。
不合格者も強い
司法書士試験は合格率5%と狭き門であるため、合格に近い方も一定数不合格になってしまいます。
令和5年では択一式試験を突破した人は約2,400人です。
その中で記述式で基準点落ちとなった人は約半数の約1,200人です。
その中で基準点ににあと0.5〜3点足りずギリギリで落ちてしまった人は約240人です。
何が言いたいかというと、こういった合格に限りなく近い方が不合格になり、来年の試験のライバルとして競っていく必要がある、ということです。
既に述べた通り、私は2回目の試験で総合点より10点高い点を取ったのに記述式で1点足りず足切りになってしまいました。
また、中には記述式は大変よく出来たが択一であと1問足りず足切りで記述は採点すらしてもらえなかった方もいるでしょう。
合格者は例年600人程度なので、この少ない枠をこのような昨年惜しかった人たちと争い上位5%に入る必要があります。
試験の難易度
合格率だけでなく、科目も多く、記述式の試験もあり、試験そのものも難しい試験になります。
具体的に何が難しいかは以下記事で記載しています。
記述式の配点変更
令和6年度の試験から記述式の点数が従来の点数の2倍となることとなりました。
何が言えるかと言うと「試験の不確実性が高まる」ということです。
択一式であれば正誤は明らかで対策が立てやすいため、択一で高得点を狙って記述式は基準点程度を取るという「択一逃げ切り」という戦略がありましたが、記述式は採点方法が明らかにされていないため、その点不確実性が高まります。
また、従来の択一逃げ切りという作戦が使えなくなり、これまで以上に記述式についてしっかり勉強時間を積み重ね得点することが必要となります。
まとめ
以上が司法書士試験の厳しい一面でした。
このように、司法書士試験は難関な試験でありますが、「正しい方向」で努力することにより合格は十分目指せます。
私は働きながら、子育てしながらというあまり勉強時間が取れない状況でしたが勉強期間は2年半、3回目の受験で合格することが出来ました。
ただし、そのためにはきちんと戦略を立てて正しい勉強法で勉強する必要があります。
効率的に学習を進めるためには予備校の活用がオススメです。
私は伊藤塾の入門講座
![]() で学んで合格しました。
で学んで合格しました。
【伊藤塾で合格しました】伊藤塾 司法書士講座の感想、口コミや評判
独学で挑戦してみたい方は以下をご参照ください。
これから受験される方の参考になれば幸いです。
✔️ 試験についてもっと知りたい方へ
短期合格のコツは?近年の出題傾向は?を知りたい方は以下、資料請求するだけで無料で貰える「非常識合格法」がオススメ
※本来1500円程度の書籍です。
以下リンクから資料請求できます。いつまでもらえるか分からないのでお早めに
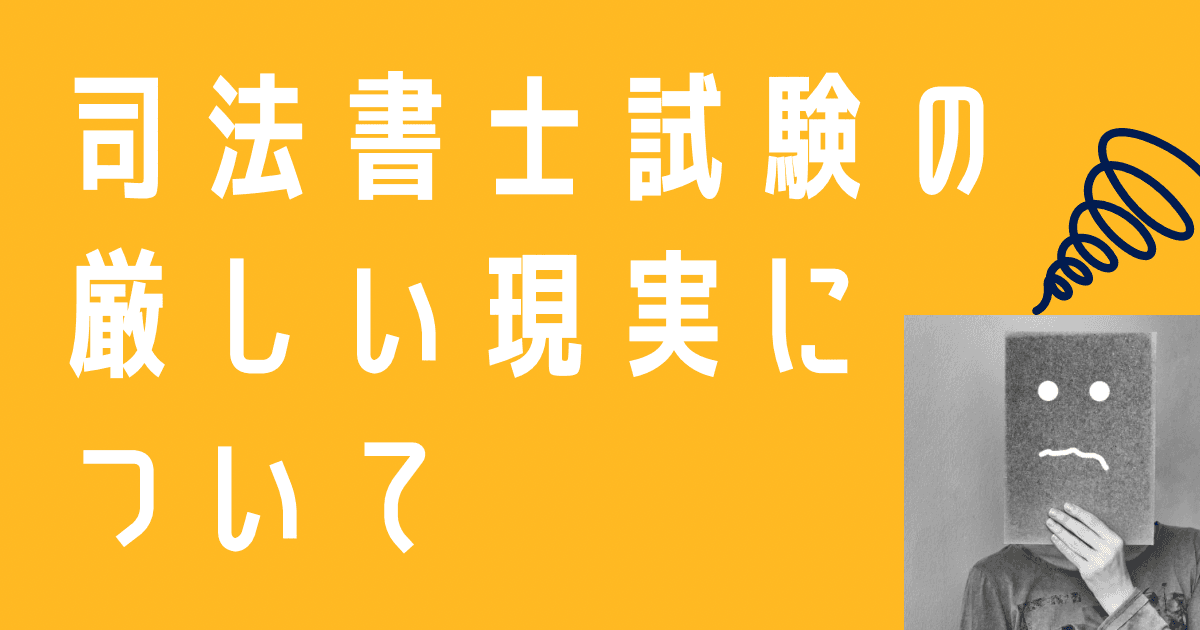

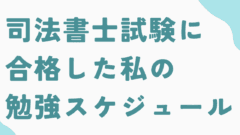
コメント