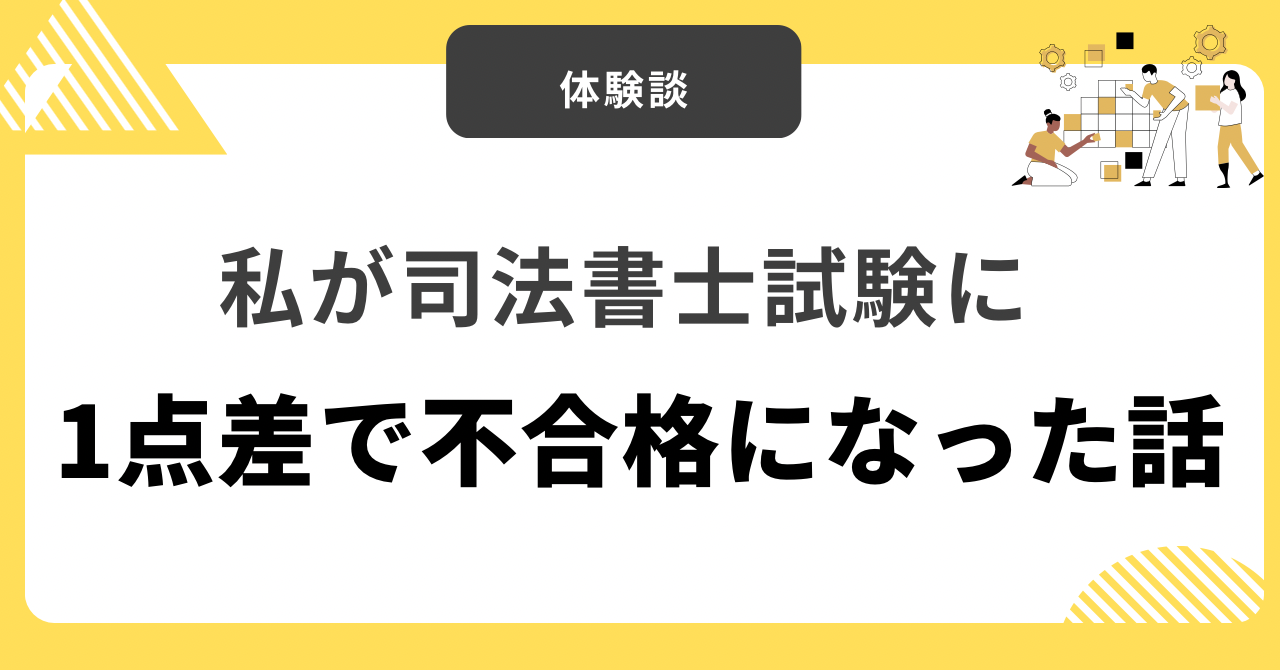こんにちは、司法書士試験合格者で宅建士試験合格者のつばさです。
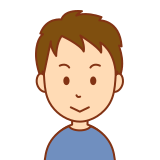
宅建士試験が気になっている

ダブルライセンスとして宅建士試験を検討している
両方の試験に合格した私が司法書士試験受験生が本試験後に宅建士試験の受験をオススメする理由について、記載したいと思います。
※こちらは司法書士の本試験後に宅建士試験の受験をオススメする記事になります。本試験が終わるまでは司法書士の勉強に絞った方が無難です。
✔︎この記事を読んで得られること
- 司法書士試験受験生に宅建士試験をオススメする理由が分かる。
- 宅建士試験も挑戦した受験生のリアルな感想が分かる
結論
司法書士試験受験生は宅建士試験の受験をすることはオススメです!
以下の4点から理由を書いてみたいと思います。
✔︎宅建士試験の受験をオススメする理由
- 権利関係(民法)の学習は不要
- 試験の時期が良い
- 司法書士試験で鍛えた力が活かせる
- 勉強習慣の継続
宅建士試験の受験をオススメする理由
権利関係(民法)の学習は不要
まずは宅建士試験の試験科目を見てみましょう。
・宅建士試験の科目 (全50問)
①権利関係 14問
②宅建業法 20問
③法令上の制限 8問
④税その他 8問
権利関係は主に民法です。一部不動産登記法と区分所有法、借地借家法も含みます。
こちらは司法書士試験でも主要科目であるため受験生は当然学習済みですが、見てわかる通り、権利関係は試験問題の約3割を占め、宅建業法に次ぐ主要科目であることがわかります。
民法は司法書士試験で学習済のため宅建用に特別な対策は不要です。現在お使いのテキストがそのまま使えるでしょう。
また、不動産登記法については確実にとっておきたいところですね。
借地借家法や区分所有法については、知識が無いと解けない問題もありますが、そんなに量も多くないので、何度かテキストや過去問を回せば得点出来ると思います。
※私はR5年度の試験の権利関係は13/14でした。
また、民法は一朝一夕での学習が難しいため、多くの宅建士受験生は民法を苦手とします。
そのため比較的得点しやすい宅建業法を中心として、勉強を進める受験生が多い傾向にあります。
司法書士試験受験生は権利関係を学習する時間を割かなくて良いため、その分他の3科目を中心に勉強が可能です。
この時点で司法書士試験受験生は大きなアドバンテージがあることが分かります。
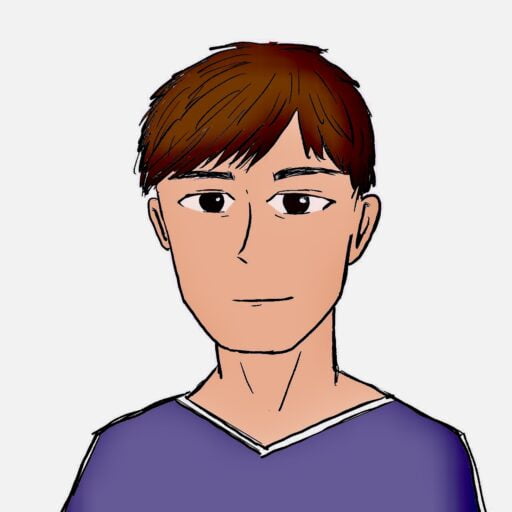
民法は司法書士試験でも重要科目で多くの勉強時間を割いて、広く深く学ぶ科目になるため宅建試験での権利関係は満点も狙えます。
理由 試験の時期が良い
オススメする理由のひとつとして「宅建士試験の時期が良い」ことも挙げられます。
宅建士試験の受験スケジュールは以下になります。
✔︎宅建士試験の受験スケジュール
・7月に受験申込み
⬇︎
・10月の第3日曜日 試験
⬇︎
・11月 合格発表
ご覧の通り、7月に司法書士試験の本試験が終わってから受験の申し込みが始まり、10月に司法書士試験の合否が出るまでの期間が宅建士試験の勉強期間になります。
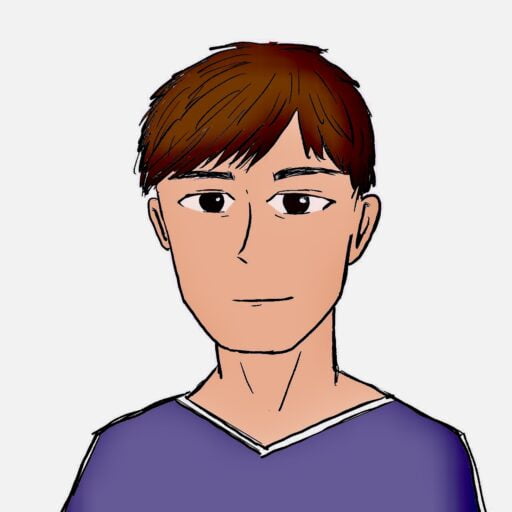
私も司法書士試験後に宅建の受験を申し込みました。
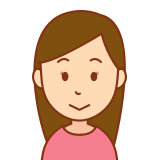
本試験後からでも宅建の本試験に間に合うの?
上記の通り、権利関係(民法)の勉強は時間を掛ける必要がないため、それ以外の対策をすれば3ヶ月の勉強期間でも十分、宅建の合格圏内に入ることが出来ます。
司法書士の合否が出るまでは司法書士試験の勉強にも手がつかない、気持ちの切り替えが難しいという方も多いと思います。
ただ、合否発表まで何もしないのも勿体無いのでその間、気持ちの切り替えとして宅建業法の勉強をしてみるのはいかがでしょうか。
司法書士試験で鍛えた力が活かせる
過酷な司法書士試験に挑戦した受験生の皆様にはとても大きな力が身についています。
例えば以下が挙げられます。
・択一問題の解くスピード、時間配分
➡︎宅建も2時間で50問を解くという時間的にタイトな面もありますが、司法書士試験での午後の試験で時間管理や肢の切り方、問題の解く順番など含め、十分なくらい鍛えられているはずです。
・司法書士受験生は択一式試験に強い
➡︎過去問を何度も何度も繰り返し解き、正確な知識を身につけることは司法書士試験受験生の強みです。
宅建試験についても過去問学習は要となるため、過去問を中心とした学習で十分合格を狙えます。
それに宅建士試験は択一式試験しかありません。しかも問題は4択です。
勉強習慣の継続
わたしは司法書士の本試験後、2週間程度勉強していませんでしたが、2週間だけでも期間が空くと、再び勉強を開始するのにエネルギーがいりました。
これが筆記合格発表の10月まで何もしていなかったらと思うと恐ろしいです…
せっかく付いた勉強習慣を無にしないためにも何かしらの勉強を継続することをお勧めします。
まとめ
司法書士試験受験生は他の受験生より負担なく宅建士試験に挑戦出来るためオススメです!
宅建試験の概要について
以下の記事で宅建試験の概要について簡単に記載しています。

私が宅建士試験の勉強をした方法
宅建の勉強を始めた時、司法書士試験の経験もあったので、最初は独学で勉強しようと思っていたのですが、これは講座を取った方が効率が良いと、スタディングの宅建士コースを受講しました。
その経緯とオススメの予備校について以下で記載しています。
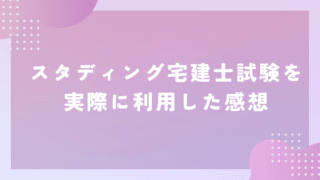
宅建士試験についてもっと知りたい方へ
✔️ 試験についてもっと知りたい方へ
短期合格のコツは?近年の出題傾向は?を知りたい方は以下、資料請求するだけで無料で貰える「非常識合格法」がオススメ
※本来1500円程度の書籍です。
以下リンクから資料請求できます。いつまでもらえるか分からないのでお早めに