こんにちは、行政書士試験合格者のつばさです。
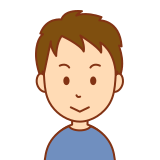
一般知識ってどう対策すればいいの

捨ててもいいって聞いたけど

足切りにならないか怖い
行政書士試験は、幅広い知識を要求する難関の試験の一環として、一般知識科目が存在します。
ただし、一般知識は範囲が広いため対策が立てにくいです。ではどのように対策をすればいいのか、この科目を得点源するためのアドバイスと取り組み方法を紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
✔︎本記事の信頼性
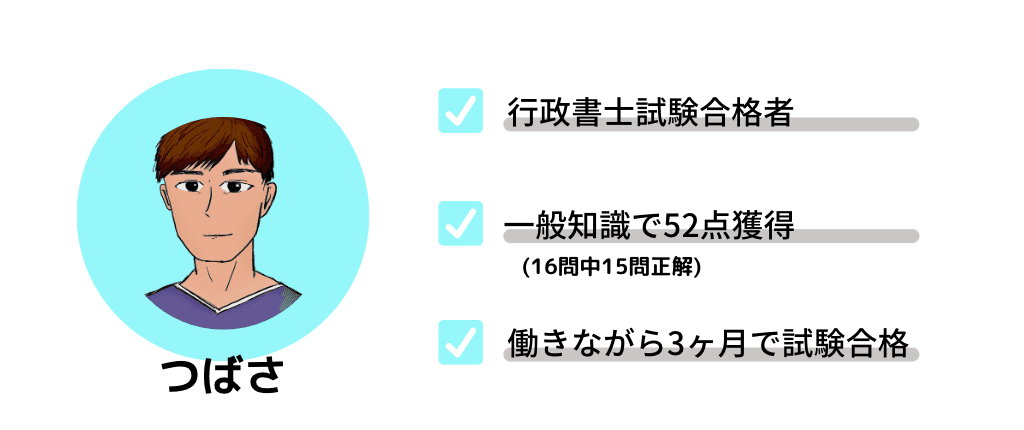
そんな私が行政書士試験の一般知識への対策方法について、記載したいと思います。
✔︎この記事を読んで得られること
- 一般知識への対策方法が分かる。
- 一般知識を捨ててはいけない理由が分かる
はじめに
行政書士試験は年々難化していることもあり、予備校利用が効率的です。
以下、私のおすすめです。
伊藤塾
![]() ・・・法律初学者や基礎からしっかり学びたい方向け
・・・法律初学者や基礎からしっかり学びたい方向け
アガルート・・・合格特典が破格、効率良く学びたい方向け
スタディング
![]() ・・・価格が破格、スキマ時間で学びたい方向け
・・・価格が破格、スキマ時間で学びたい方向け
一般知識科目とは
行政書士試験には大きく分けて、法律科目と一般知識科目の2つに分けられます。
この科目は、法律の知識だけでなく、経済学、政治学、社会科学、歴史、地理など、幅広い学問領域にわたる知識を問われることが特徴です。
一般知識科目の役割
一般知識科目は、行政書士に必要な幅広い知識を持っているかどうかを評価するものです。
行政書士は、様々な業務領域で法的なアドバイスを提供し、行政手続きをサポートする役割を果たします。そのため、法律のみならず、経済や社会情勢にも精通していることが求められます。
一般知識の出題分野
一般知識科目の中でも更に①政治経済・社会②情報通信・個人情報保護法③文章理解と3つの分野に分けられます。
①政治経済・社会
センター試験の社会科目のイメージ
世界各国の政治や日本の経済問題、時事問題や社会現象に関する問題などから幅広く出題されます。
②情報通信・個人情報保護法
回線、通信など情報通信に関する問題や、個人情報保護法や公文書管理法といった法律からの出題があります。
③文章理解
学生時代の現代文の試験のイメージ
空欄補充や文章の並び替え、要旨把握などを問われます。
一般知識科目はその範囲の幅広さゆえに、受験生にとっては対策が難しいと感じる人も多いです。
しかし、適切な勉強計画や効果的な学習方法を用いれば、充分に対策できる科目です。正しいアプローチを取ることで、一般知識科目を克服し、得点源にしましょう。
※行政書士試験全体の概要については以下記事で詳しく書いています。
配点について
行政書士試験では一般知識の出題数は60問中14問になります。
配点としては300点中、56点です。
出題数、配点については行政法や民法に次ぐレベルとなり、後ほど記載しますが一般知識だけで足切り点が設定されているため、試験対策上非常に重要な科目であることがわかります。
分野別では政治経済が16問中、7〜8問程度と一番大きくなっています。
足切り点について
行政書士試験には足切り点があり、それぞれ一つでも足切り点を満たさないとそれだけで不合格となってしまいます。
法令科目は122点、一般知識は24点以上出ないと足切り点として不合格になります。
つまり、いくら法律科目で高得点が取れていても一般知識で24点未満だと不合格になります。
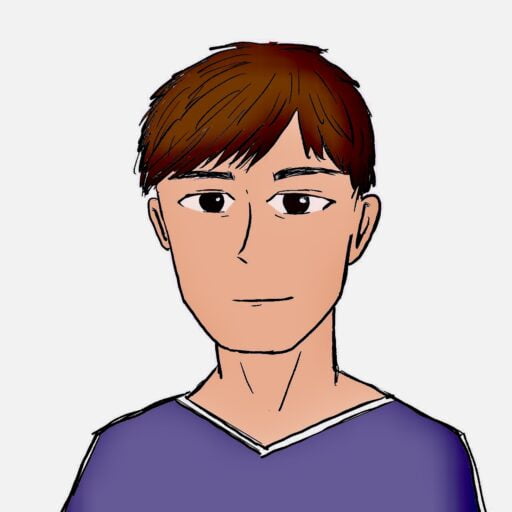
法律科目は対策が立てやすいのですが、一般知識は範囲も広く対策が立てにくいので私も足切りは恐れていました。
分野別、私が行った対策について
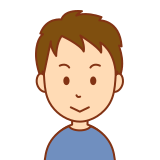
一般知識が配点が大きく重要なのは分かった、じゃあ主要科目と並んで勉強の柱にしよう
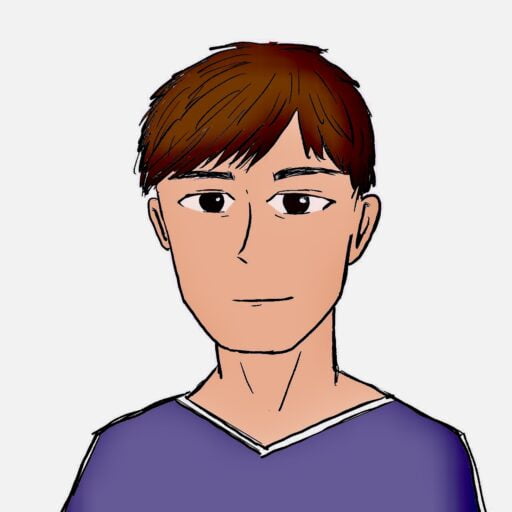
確かに一般知識も大事なのですが、政治経済など費用対効果が小さい分野もあります。
的を絞って必要な箇所だけ勉強しましょう。
一般知識は試験範囲が広く事前の準備も難しいです。
例えば政治経済は得点が大きいですが、じゃあ今からセンター試験の教材を買ってきて準備するかというとそれはオススメ出来ません。
理由としては範囲が広すぎるため、広すぎる勉強範囲に対して得点出来るコスパが悪いためです。
ただ、個人情報保護法などは比較的得点に結びつきやすいです。
では合格者の私はどう対策を掛けていたのかご紹介したいと思います。
政治経済・社会
こちらの分野は前述の通り、試験範囲が広すぎて、費用対効果が良くないため私もほとんど対策をしていません。
恐らくこの分野をしっかり対策する受験生も少ないと思います。(というか対策をしても得点に結びつくかは微妙)
対策出来ることとすれば、世の中のニュースにはアンテナを張っておくことが必要です。
時事問題からの出題もあるため一般常識で答えられる問題もあります。
また、この分野は正解の肢を絞り込むというよりは、明らかに異なる問題が無いかだけを探すようにしましょう。
案外、肢の一つに簡単なものや一般常識で解けるものがあったりします。
正解が絞り込めなくても、1問、もしくは2問、明らかに異なる肢が切れるだけで5択から4択or3択まで絞れますのでそれだけで正答率は少し上がります。
情報通信・個人情報保護法
こちらは一番対策がしやすい分野になります。
過去問や問題集に載っている問題くらいは繰り返し解き、ある程度は答えられるようにしましょう。
過去問で対策をしていれば解ける問題も他の分野よりは多いです。
また、情報通信では例えば「ファイアウォール」「5G」「光通信」など日常生活でも耳にする単語も多いため、頭に入りやすいです。
選択肢も「5Gとは〇〇のことである」と定義を聞くだけの出題が多いので、単純に知っていれば得点出来るものも多く、対策しておいて損はありません。
文章理解
こちらも一見、対策が不要に見えますが、対策出来ることはあります。
確かに、過去問と同じ文章が出てくることはないでしょうから過去問の問題を覚える必要はありません。
ただし、①出題傾向に慣れる。②長文に慣れる意味で、過去問を検討するのは良いと思います。
①出題傾向に慣れる
文章理解は文章の並び替えや穴埋め問題がありますが、文章の接続詞から答えを導くなどテクニック的に解けるものもあったりします。そのため過去問でどんな問われ方をするのか、事前に確認しておくのは良いと思います。
②長文に慣れる
私もそうでしたが、日頃そんなに長い文章を読むことは無いと思います。
そのため、長い文章に慣れる意味でも過去問に触れておくのは良いです。
また、行政書士試験は試験中の時間配分重要になりますので読解問題はどれくらい解くのに時間が掛かるのか、どれくらい時間を掛けていいのかを把握し、過去問を通してシミュレーションしましょう。
合格へのアドバイス
一般知識科目に挑戦する受験生の皆さんへ向け、私の実際の経験から一般知識対策についてのアドバイスを記載します。このアドバイスを通じて、試験に臨む際の何かのヒントになれば幸いです。
アドバイス1: 早めのスタート
一般知識対策はなるべく早めに少しずつ始めることをオススメします。
一般知識科目は配点も大きく、広範な知識を要求されるためしっかりとした対策が必要ですが、だからといって行政法や民法を差し置いてバリバリ勉強する科目ではありません。あくまで行政書士試験で優先すべきは行政法と民法です。
一般知識対策はなるべく早めに実施し、試験直前は行政法や民法へ時間を当てられるようにしましょう。
アドバイス2: 過去問の積極的活用
一般知識は過去問を解いても意味がないのでは?と思われるかも知れません。
確かに政治経済分野は過去問を検討する必要は無いでしょう。
また、文章理解も過去問と同じ問題が出ることはないため問題や答えを覚える必要はありません。
ただし、個人情報保護法や情報通信については出題範囲も限られるため過去問からも出題もあります。
また、文章理解も一見、過去問を解く意味はなさそうに感じますが、実際の試験問題を解くことで、どんな問題が出るのか、どんな問われ方をするのかなど、出題傾向を把握することができます。
そのため過去問は一般知識点数向上のための貴重なツールです。
過去問題も実際に解いてみてどれくらい取れるのか確認し、自分の実力を把握しましょう。
まとめ
一般知識科目に対する対策方法やアドバイスについて詳しくご紹介しました。
行政書士試験に合格するためには、一般知識科目をしっかりと攻略することが欠かせません。ですが、行政法や民法そっちのけでバリバリやる科目ではありません。
例えば1日15分は一般知識の対策に充てるなど毎日少しずつ対策をしてくことが必要です。
一般知識科目の対策は難しいかもしれませんが、コツコツ対策することで得点源にすることが出来ます。
私が行政書士試験の勉強をした方法
私は独学3ヶ月で合格することが出来ました。
その記録は以下の記事に記載しています。
✔️ 試験についてもっと知りたい方へ
短期合格のコツは?近年の出題傾向は?を知りたい方は以下、資料請求するだけで無料で貰える「非常識合格法」がオススメ
※本来1500円程度の書籍です。
以下リンクから資料請求できます。いつまでもらえるか分からないのでお早めに




コメント